
情報システム部門には、システム連携図やネットワークチャートというものが、A3用紙で1枚程度で必ずあるはずです。ほとんどの場合は、ベンダーさんが書いてくれたものか、それに書き足したものが多いかと思います。このネットワークチャートやシステム連携図とは、一体誰のためにあるのでしょうか。実は、これはシステム部門のためだけではありません。
このネットワーク連携図は、一見、非常にわかりにくく、システム部門以外の人が見ると専門用語があって、内容についてはよくわからないものです。しかし、情報システムのメンバーは、それを良しとして、自分たちの存在価値があると思っている人たちも多くいました。
自分たちしか理解できないようなネットワーク連携図は、あまり意味がありません。ネットワークチャートやシステム連携は、システム部門以外の人にも理解してもらう必要があります。その中で最も理解してもらいたい人は社長です。社長が理解していれば、新しいシステム投資やセキュリティ投資に苦労する必要はありません。むしろ、社長からトップダウンで命令が来るくらいが良いのです。それだけITリテラシーが高いということは、デジタル化の促進に関心が高いということになります。

この時代、社内のシステム連携がどうなっているかわからない経営陣は、はっきり言ってマズいです。現在においては、仕事の全てがデータ化され、コンピューターで行われている時代です。昔の手書き時代とは違います。稟議書もデジタル化されて、ワークフローのシステムで動かしている時代です。そうした時代の中で、自分たちが日々扱っている経営情報が、どのように社内で流れて生成されているのかを理解しておくべきです。
そして、もう一つ、社会的責任として情報漏洩のリスクがあります。社内の自社のデータが漏洩すると自社がダメージを受けるだけで、まだ少しは良いのかもしれませんが、個人情報が漏洩するとその人たち全員に迷惑かかります。個人情報は絶対に漏洩させてはいけません。そのためにも、個人情報がどこのサーバーにあり、どういった管理を誰がいつしているのか、ということは経営者として常に把握しておくことが重要です。
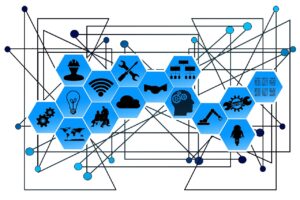
情報システムの技術には専門用語が多くあります。それらの専門用語を使って、ネットワークチャートやシステム連携図を作成しても良いのですが、必ず、第三者が見てもわかるような説明を補足でつけておきましょう。
システム連携図やネットワークチャートは「我々の専門分野だから、経営陣に対して説明してもどうせわからない」と考えずに、難しい言葉でも、わかりやすく丁寧に説明して、社内のITリテラシーを高めていくことは情報システム部門の大切な仕事なのです。
では、システム連携図やネットワークチャートを第三者が見てもわかりやすく書くためには、どうすればいいのでしょうか。すべてを1枚の用紙にまとめないで、それぞれのシステム機能ごとに1枚ずつ説明を入れてフロー図で説明をすることをおすすめします。
例えば、バックアップについてとか、ログイン認証についてとか、売上データの夜間バッチ処理についてなど、テーマごとにパワーポイントのスライドで資料を作って丁寧に説明をしていきます。そうするとA3用紙でたった1枚のシステム連携図やネットワークチャートだったものが、パワーポイントでのスライドが50ページ程度のものになります。
その説明には、多くて2時間くらいはかかるでしょう。1年に1回でも良いので、社長に話を聞いてもらってください。セキュリティーの重要性や、システム連携や、システム活用方法の現状を理解してもらい今後の課題も共有するのです。
こうした自部門以外へのアピールや相手にわかりやすくわかってもらうように工夫し、意図的に機会を持って、ITリテラシーを上げていくことはITマネージャーの極めて重要な仕事の1つです。
